こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
― 糖代謝の舞台裏:NADHのゆくえと「乳酸シャトル」の真実 ―
運動中、私たちの筋肉は絶え間なくエネルギー(ATP)を消費します。このATPを効率よく作り続けるために鍵を握るのが、「NADH(還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)」という物質です。
今回は、糖質がエネルギーに変わるプロセスの裏側で起きている、NADHの輸送と乳酸の知られざる役割について解説します。
■ 解糖系:エネルギー産生の第一歩
糖質(グルコース)が細胞質で分解され、ピルビン酸になる過程を「解糖系」と呼びます。このプロセスでは、1分子のグルコースから以下の物質が生まれます。
- 2つのATP(即戦力のエネルギー)
- 2つのNADH(エネルギーの「素」となる電子運搬体)
このNADHが持つエネルギーを最大限に引き出すためには、ミトコンドリアへと運ぶ必要があります。
■ 「ミトコンドリアの壁」とシャトル機構
ATPを大量に産生する「電子伝達系」は、ミトコンドリアの内部にあります。しかし、細胞質で作られたNADHは、そのままではミトコンドリアの膜を通り抜けることができません。
そこで、荷物をバケツリレーのように受け渡す「シャトル機構」が登場します。
- リンゴ酸-アスパラギン酸シャトル: 主に心筋や肝臓、遅筋で働き、エネルギー効率が高い。
- グリセロリン酸シャトル: 主に速筋で働き、速度は速いがエネルギー効率はやや落ちる。
これらのシャトルによって、NADHの持つ「電子」がミトコンドリア内へ送り込まれ、大量のATPが作られます。
■ 高強度運動で起きる「交通渋滞」
しかし、強度の高い運動(ダッシュや激しいトレーニング)では、このシャトル機構が限界を迎えます。
- 濃度差の壁: 運動中、筋肉内の乳酸やNADHは10mmol/kg以上に達しますが、シャトルに関わる物質(リンゴ酸など)は0.1mmol/kg程度しかありません。
- 速度の限界: 爆発的な糖分解のスピードに、シャトルによる電子輸送が追いつかなくなるのです。
ここで、かつて疲労物質と呼ばれた「乳酸」がヒーローとして登場します。
■ 救世主としての「細胞内乳酸シャトル」
シャトルが間に合わないとき、細胞は乳酸を利用したショートカットを開始します。
- 細胞質: ピルビン酸とNADHが反応し、「乳酸」と「NAD+」に変わる(ここでNAD+が再生され、糖分解が止まらずに済む)。
- ミトコンドリア: 乳酸がミトコンドリア内へ直接取り込まれる(MCT1経由)。
- 再変換: ミトコンドリア内で乳酸が再びピルビン酸に戻り、同時にNADHが再生される。
これがジョージ・ブルックス博士の提唱した「細胞内乳酸シャトル」です。これにより、シャトル機構がパンク状態でも、ミトコンドリアにエネルギー源を届けることが可能になります。
■ 「NAD+の再生」こそが生命線
ここで最も重要なのは、「NAD+」の確保です。
糖を分解し続けるには、常に「空のトラック」であるNAD+が必要です。もし全てのNADHを無理にミトコンドリアへ送ろうとすると、細胞質内のNAD+が不足し、エネルギー産生そのものがストップしてしまいます。
乳酸を作るプロセスは、余ったNADHを一時的に処理し、「糖を燃やし続けるための場所(NAD+)を空ける」という、極めて合理的なリサイクルシステムなのです。
■ まとめ:精密なエネルギー・バランス
- NADHはATPを作るための貴重な燃料だが、ミトコンドリアの膜を通れない。
- 通常はシャトル機構が電子を運ぶが、高強度運動では処理能力を超える。
- 乳酸は、エネルギーをミトコンドリアへ運ぶ「第2の運送業者」であり、同時に糖分解を維持する「調整役」である。
「乳酸が出るのは追い込んでいる証拠」なのは間違いありませんが、それは体が「限界の中でも効率よくエネルギーを作り続けよう」と高度な工夫をしている証でもあるのです。
※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。
健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。
体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。
📚 引用・参考文献
本記事の解説は、以下の研究成果および生理学理論に基づいています。
- Brooks, G. A. (1985).Lactate: glycolytic end product and oxidative conditioning substrate. Medicine and Science in Sports and Exercise, 17(1), 22-31.
- (乳酸シャトル理論の原点となる論文。乳酸が酸化基質であることを提唱)
- Brooks, G. A. (2018).The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory. Cell Metabolism, 27(4), 757-785.
- (細胞内・細胞間乳酸シャトルに関する最新の知見とメカニズムの総括)
- Hatta, H. (2015).Lactate and Exercise Physiology. (八田秀雄 著『乳酸と運動生理学』)
- (シャトル構成物質の濃度差と、乳酸によるNADH輸送の必然性に関する日本を代表する知見)
- Gladden, L. B. (2004).Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium. The Journal of Physiology, 558(1), 5-30.
- (乳酸を単なる代謝産物ではなく、シグナル分子や燃料として捉えるパラダイムシフトの解説)
- Robergs, R. A., Ghiasvand, F., & Parker, D. (2004).Biochemistry of exercise-induced metabolic acidosis. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 287(3), R502-R516.
- (解糖系におけるプロトン産生と乳酸生成の化学的意義についての詳細な分析)

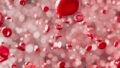

コメント