こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
糖質と脂質、どっちが使われている?
「安静にしているとき、体は何を使ってエネルギーを作っているの?」
「運動をすると脂肪は使われなくなるの?」
こういった質問をいただくことがあります。
糖質と脂質は、どちらも私たちの体にとって大切なエネルギー源。
しかし、その利用バランスは運動の強度によって大きく変わるんです。
今回は「無酸素性作業閾値(AT)」を基準に、糖質と脂質の使われ方を解説していきます。
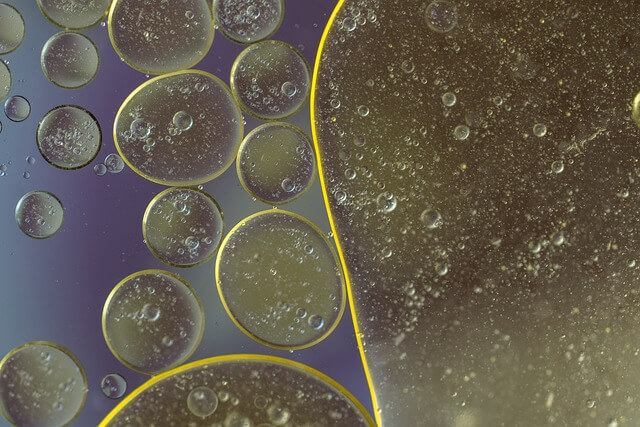
◆ 安静時は脂質優位!でも「燃えやすい」わけじゃない
何もしていない状態(=安静時)、私たちの身体は糖質と脂質をどんな割合で使っているのでしょうか?
答えは──
糖質:脂質 = 1:2
つまり、安静時は脂質が糖質の2倍使われているということです。
これは意外に感じる方も多いかもしれませんね。
ただし、これは「割合」の話です。
「安静時のほうが脂肪が燃える!」という意味ではないので注意してください。
総エネルギー消費量は運動時の方がずっと多いのですから。
◆ 運動強度が上がるとどうなる?
▶ 有酸素運動レベルでは
運動を始めると、筋肉の活動によりエネルギー需要が高まります。
すると、糖質の利用が増加します。
このとき、脂質の利用がゼロになるわけではありません。
脂質の量も増えていますが、糖質の利用割合が上回る形になっていくのです。
▶ 無酸素運動レベルになると
さらに強度が上がり、80%VO₂max(最大酸素摂取量)のレベルに達すると、
糖質:脂質=2:1という比率になります。
ここで初めて、脂質の利用が実際に減少していくのです。
◆ 無酸素性作業閾値とは?
この「糖質の利用が急激に増え、脂質の利用が低下し始めるポイント」が、
無酸素性作業閾値(Anaerobic Threshold:AT)です。
▽ ATを境に、運動強度でこう変わる!
AT以下の運動強度 → 有酸素運動
→ 脂質の割合が多いが、糖質も一定使われる
AT以上の運動強度 → 無酸素運動
→ 糖質の利用が急増、脂質の利用は抑制される
このようにATは、糖質と脂質の使われ方の「分岐点」とも言える存在なんです。
◆ なぜ脂質の利用が減るのか?
ここからが本題。
なぜ運動強度が上がると脂質の利用は下がってしまうのでしょうか?
結論から言うと、まだ完全には解明されていません。
ただ、いくつかの“仮説”があります。
◆ 脂肪組織への血流が減る
運動強度が高くなると、筋肉への血流が優先され、脂肪組織への血流が減少します。
その結果、脂肪分解が落ち、血液中の遊離脂肪酸(FFA)の濃度も低下。
結果として、脂質の利用が抑制される可能性があります。
◆ 酸素供給のスピードと効率の問題
脂質は糖質よりもエネルギーに変えるのに時間と酸素が必要です。
高強度ではスピーディーにエネルギーを供給しなければならないため、
手間のかかる脂質より、すぐ使える糖質が優先されるという考えもあります。
◆ 酵素の働き・細胞内のpH変化など
他にも、
・脂肪酸輸送体(CPT1)の働きがpH低下で落ちる
・マロニルCoAが脂質輸送を阻害する
・乳酸が脂肪燃焼を抑制する
といった、細胞内の環境変化も関連していると考えられています。
◆ まとめ:脂肪を燃やしたいなら、ATを超えない運動を!
・安静時は脂質が多く使われている(糖質:脂質=1:2)
・運動強度が上がると糖質利用が増える
・無酸素性作業閾値(AT)を超えると、脂質の利用は下がる
脂肪をエネルギーとして効率よく使いたい場合、
ATを超えない中強度の運動がもっとも効果的と言えるでしょう。
脂肪を「燃やす」ことと「汗をかくこと」や「キツさ」は必ずしも比例しません。
目的に応じて、運動の“強度”も意識してみてくださいね。
※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。
健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。
体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。
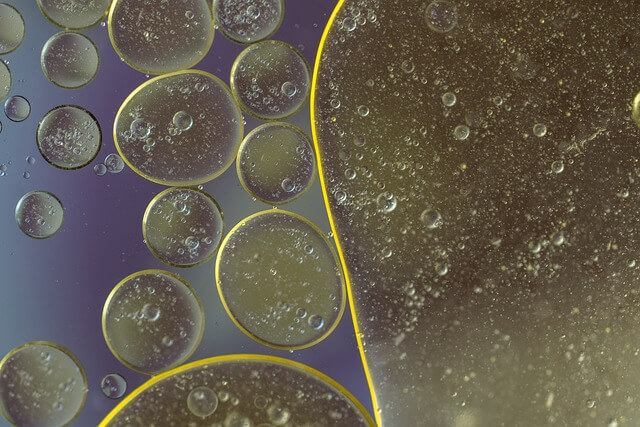

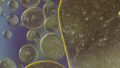
コメント