こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
「糖質」「脂質」「たんぱく質」──人がエネルギーとして使える三大栄養素の中で、脂質はもっとも手間がかかるエネルギー源といわれています。
今回は、「なぜ脂質は手間がかかるのか?」「それでもなぜ脂質は大切なのか?」について、代謝経路を追いながら解説していきます。

脂質の代謝は複雑な道のり
脂質(中性脂肪)は、まず脂肪細胞で「脂肪酸」と「グリセリン」に分解されます。
この脂肪酸は、水に溶けないため、そのままでは血液を流れることができません。
そこで、「アルブミン」というたんぱく質にくっついて、ようやく筋肉まで運ばれます。
筋肉に届いた脂肪酸は、脂肪酸トランスポーターによって筋細胞に取り込まれ、そこからさらに「CPT1(カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1)」と「CPT2」という酵素の働きで、ミトコンドリア内部へと移送されます。
ベータ酸化 → TCA回路へ
ミトコンドリアに取り込まれた脂肪酸は、「β(ベータ)酸化」と呼ばれるプロセスで、炭素を2個ずつ分解されていきます。
このときに生成されるのが「アセチルCoA」というエネルギーの元になる物質です。
アセチルCoAは、その後「TCA回路(クエン酸回路)」という反応経路に入り、酸素を使って完全に酸化(燃焼)され、最終的にATPというエネルギーを生み出します。
糖質と比べると…脂質は効率が悪い?
ここまで読んでわかるように、脂質は分解・輸送・ミトコンドリア内での処理など、多くのステップが必要です。
一方、糖質(グルコース)は、水に溶けやすく、分解も比較的簡単。
そのため、運動強度が高くなると糖質の利用が優先され、脂肪の利用は減少していきます。
これは、脂質の代謝が糖質よりも“手間がかかる”ことが理由のひとつと考えられています。
たんぱく質よりは扱いやすい?
とはいえ、脂質が「使いにくいエネルギー源」かといえば、そうでもありません。
たんぱく質(アミノ酸)は「窒素」を含んでいるため、エネルギーとして使う際に窒素を取り除く手間(脱アミノ反応など)が必要です。
また、水に溶けにくい性質を持つアミノ酸も多く、代謝においてはさらに複雑な処理が必要になります。
つまり、脂質は糖質と比べれば面倒だが、たんぱく質と比べれば扱いやすいといえるでしょう。
実は安静時には脂肪が主役
安静時、つまり運動していない状態の私たちの体では、全エネルギーの約70%が脂質から供給されています。
つまり、体を動かしていないときには、脂質は最もよく使われているエネルギー源なのです。
このように、脂質は手間がかかるとはいえ、運動強度が低いときや安静時には効率よく使われるエネルギーであり、私たちにとって非常に重要な存在といえます。
まとめ
・脂質の代謝には、脂肪細胞から筋肉への輸送・ミトコンドリアへの取り込み・β酸化・TCA回路など、多くのステップが必要
・糖質と比べると“手間がかかる”が、たんぱく質と比べれば扱いやすい
・安静時には脂質が主要なエネルギー源となっている
・脂肪を効率よく使うには、運動や代謝を活性化する生活習慣が大切
※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。
症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。


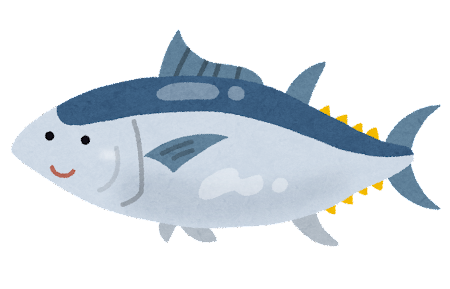
コメント