こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
脂肪といっても、すべてが同じわけではありません。
脂肪酸は大きく「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2種類に分類されます。
今回は、健康との関係が深い「不飽和脂肪酸」に注目していきましょう。

不飽和脂肪酸の特徴とは?
脂肪酸は炭素と水素からなる「鎖構造」を持ちます。
この炭素同士のつながり方に違いがあります。
飽和脂肪酸:炭素同士がすべて単結合(まっすぐ)
不飽和脂肪酸:炭素同士に二重結合が含まれている
この「二重結合」があることで、脂肪酸の鎖が曲がりやすくなり、脂の性質が大きく変わってくるのです。
オメガ3・オメガ6とは?
不飽和脂肪酸の中でも、特に注目されているのが以下の2つ:
・オメガ3脂肪酸:二重結合が端から3番目にある
・オメガ6脂肪酸:二重結合が端から6番目にある
これらは体内で合成できない「必須脂肪酸」であり、食事からの摂取が不可欠です。
特にオメガ3脂肪酸は、以下のような機能があると考えられています:
・細胞膜の柔軟性を高める
・炎症の抑制
・脳や神経の機能をサポート
細胞膜に柔らかさを与える脂
脂肪酸が細胞膜に取り込まれるとき、不飽和脂肪酸は二重結合によって曲がった構造をしています。
これにより、脂肪酸同士が密に詰まりにくくなり、細胞膜が柔らかく・流動性の高い状態を保てるとされています。
この柔らかさが、細胞間の情報伝達や代謝の効率などに良い影響を与えていると考えられているのです。
魚に不飽和脂肪酸が多い理由
魚の脂には、オメガ3脂肪酸(EPAやDHA)が豊富に含まれています。
これは、魚が水中で生活しているためです。
水は空気よりも熱伝導率が高く、魚は周囲の水温に強く影響を受けやすい生き物です。
そのため、体内の脂肪が固まらないように、不飽和脂肪酸を多く含むことで体を守っているとする説があります。
つまり、魚の脂は「冷たくても固まりにくい脂」なのです。
動物性脂肪と魚の脂、どちらが良い?
例えば、牛肉や豚肉などの脂には飽和脂肪酸が多く含まれ、常温でも固まりやすい特徴があります。
一方、魚の脂は不飽和脂肪酸が多いため、常温でも液体に近く、体内でも固まりにくい性質を持ちます。
そのため、健康の観点からは、魚を積極的に食べることが推奨されているのです。
まとめ
・不飽和脂肪酸は、炭素に二重結合を持つ脂肪酸
・オメガ3・オメガ6は、体に必要な必須脂肪酸
・魚にはオメガ3が豊富で、脳や血管に良い影響が期待されている
・飽和脂肪酸よりも、不飽和脂肪酸を多く含む魚の脂を選ぶことが健康的
※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。
症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。
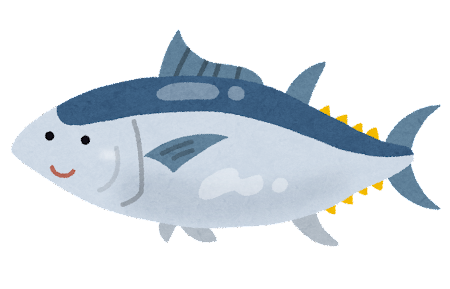

コメント