こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
なぜ乳酸は生まれるのか?
「乳酸=疲労物質」と教わった方、いまだにそう信じていませんか?
実はこの考え方、今では誤解とされています。
近年の生理学では、乳酸は単なる“老廃物”ではなく、代謝をスムーズに進めるために必要な存在であることが明らかになってきました。
そしてこの乳酸の生成には、「NAD」と「NADH」という2つの補酵素が深く関わっています。
・なぜNADHが増えると代謝が止まるのか?
・なぜ乳酸ができることでATPが生まれると言われてきたのか?
・そして、乳酸は本当に“無酸素”のサインなのか?
今回はこのテーマについて、トレーナー・運動指導者向けにも役立つ視点で、わかりやすく解説していきます。
「乳酸ができる=悪」ではなく、むしろ身体が賢くバランスを取っている証拠だった。
そんな視点で、あなたの代謝理解を一段深めてみましょう。
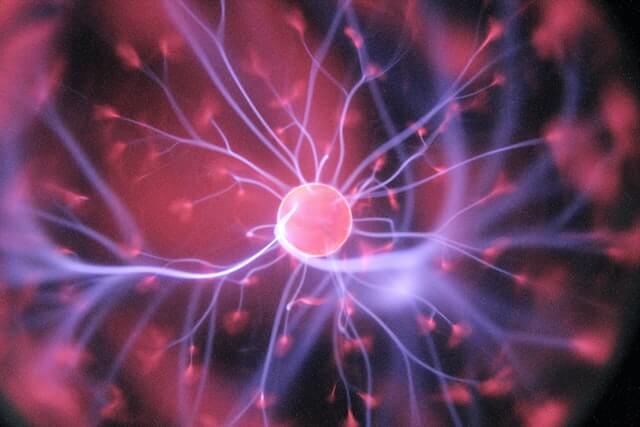
グルコース分解とNAD/NADHの関係
グルコースが解糖系によってピルビン酸へと分解される過程では、2分子のNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)が2分子のNADHに変換されます。
このNADHは、本来ミトコンドリアで電子伝達系によりATPの産生に使われる重要なエネルギー源です。
しかし、ここで問題が一つ。
NADHはミトコンドリアの膜を直接通過できないため、その処理が遅れやすくなります。
すると、NADHが細胞質内に溜まり、NADが足りなくなってしまい、グルコースの分解(解糖系)がストップしてしまうリスクが出てきます。
【NADHを処理するために乳酸ができる】
この問題を解決しているのが、乳酸脱水素酵素(LDH)の働きです。
この酵素により、ピルビン酸が乳酸に変換される際に、NADHがNADに戻されるのです。
乳酸脱水素酵素の反応(両方向)
・ピルビン酸 → 乳酸:NADH → NAD(解糖系を進めるための供給)
・乳酸 → ピルビン酸:NAD → NADH(後にミトコンドリアで再利用)
このようにして、NADが再生されることで、糖質分解を継続させることができるのです。
乳酸ができるのは“酸素がないから”ではない
これまで「乳酸ができる=無酸素状態」とされてきました。
実際、ピルビン酸をTCA回路に入れて完全に分解するためには酸素が必要です。
しかし、乳酸ができる理由はそれだけではありません。
例えば運動開始時、解糖系は急激に活性化し、一時的にピルビン酸やNADHが急増します。
この時、ミトコンドリアの処理能力を超えてしまうと、酸素があってもNADHが溜まり、代謝が停滞してしまいます。
そのため、乳酸ができることは「無酸素」状態の証拠ではないのです。
酸素がある状態でも、代謝のバランスを取るために乳酸は生み出されています。
乳酸はエネルギー源として再利用される
生まれた乳酸は不要な“老廃物”ではありません。
実際には、筋細胞や他の組織のミトコンドリアで再びピルビン酸に戻されて、TCA回路でエネルギー源として活用されます。
つまり、乳酸はNADの再生を助けながら、エネルギー回路を回す中継物質でもあるのです。
ATPと乳酸の関係|2つのATPはどこでできる?
よく「乳酸ができるとATPが2つできる」と説明されることがあります。
しかし、これはやや誤解を招きやすい表現です。
実際には、ATPはグルコース分解の途中(解糖系)で2つ生まれます。
その後に乳酸ができようができまいが、ATPの生成自体には直接関係ありません。
正しくは、
・グルコースが分解されると必ず2つのATPができる
・乳酸はNADを再生して、糖分解を続けられるようにする役割
・乳酸ができたから2つのATPが生まれるわけではない
という理解が正確です。
まとめ|乳酸とNAD/NADHは“代謝のバランス調整役”
・NADは糖質代謝のために不可欠な補酵素
・NADHが溜まりすぎると、解糖系が止まる
・それを防ぐのが乳酸脱水素酵素によるNADの再生
・酸素があっても、代謝バランスのために乳酸は作られる
・乳酸は“無酸素の証拠”ではなく、むしろ代謝を助ける存在
エネルギー代謝を理解するうえで、NADとNADH、そして乳酸の本当の役割を知ることは非常に重要です。
単なる「疲労物質」として片付けるには、あまりにももったいない働きをしてくれています。
※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。
健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。
体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。
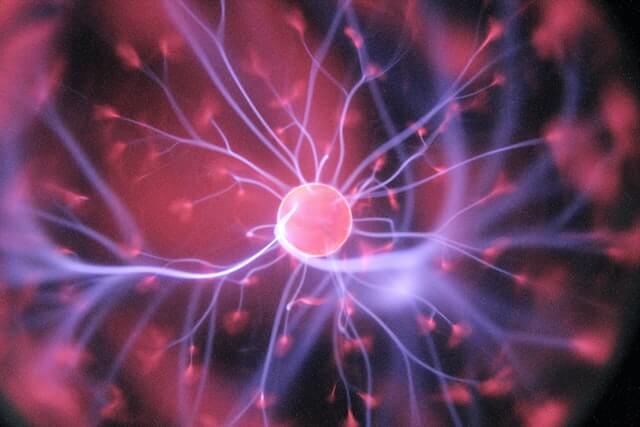

コメント