こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
乳酸=疲労物質というイメージがいまだに根強いかもしれませんが、
実際には乳酸はエネルギー源として再利用される重要な物質です。
その再利用に深く関わるのが、MCT1(モノカルボン酸トランスポーター1)という輸送体です。
今回はこのMCT1の基本的な特徴と、運動との関係性についてわかりやすく解説していきます。

■ MCT1とは?なぜこの名前?
MCT1とは、「モノカルボン酸トランスポーター1(Monocarboxylate Transporter 1)」の略称。
その名の通り、ピルビン酸や乳酸などの“モノカルボン酸”を輸送する役割を持ち、
このタイプの輸送体として最初に発見されたため「1番=MCT1」と名付けられました。
■ MCT1の輸送のしくみ|ATPを使わない?
MCT1の大きな特徴は、ATP(エネルギー)を使わずに輸送すること。
これはつまり、「濃度勾配」に従って動くということです。
・濃度が高いところ → 濃度が低いところへ
・エネルギーを消費しない受動輸送
逆に、濃度勾配に逆らっての輸送(能動輸送)はできません。
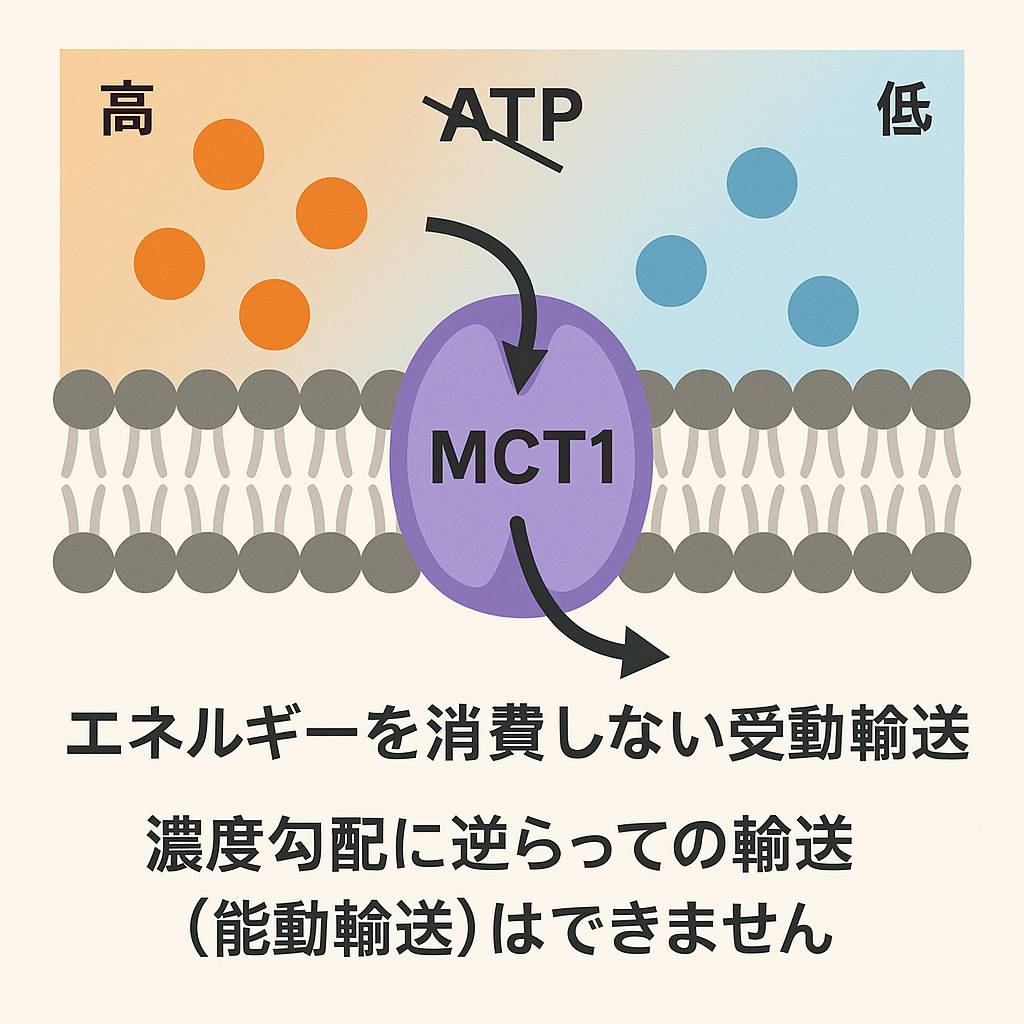
■ MCT1はどこに多いのか?
MCT1は遅筋繊維(持久力タイプの筋肉)に多く存在します。
特に、心筋には豊富にMCT1が分布しています。
これは、心臓や持久力を使う筋肉が乳酸を再利用してエネルギーに変える能力が高いことを示しています。
■ MCT1は運動で増える!
持久系のトレーニング(特に高強度の持久トレーニング)を行うと、MCT1は増加します。
【流れの例】
- 筋持久力トレーニングを行う
- MCT1の量が増加
- 乳酸の取り込み量も増加
- 乳酸を酸化して再利用できる能力が向上
- 結果として、血中の乳酸濃度が低下
つまり、MCT1が多い筋肉=乳酸をエネルギーとして使いやすい筋肉なのです。
■ 筋肥大や筋分解との関係
MCT1は筋肉の量にも影響を受けます。
・筋肥大するとMCT1も増える
・逆に、筋分解が進むとMCT1は減る
つまり、筋肉の健康維持や成長にもMCT1は深く関わっているのです。
■ 糖尿病とMCT1の関係
糖尿病になると糖の代謝能力が落ちるため、乳酸の生成量も減少します。
それに伴ってMCT1の量も減少してしまいます。
だからこそ、糖尿病の方にも運動はとても重要です。
【運動の効果】
・糖代謝が促進される
・乳酸が適度に産生される
・MCT1が増え、乳酸を有効活用できる
→ 結果として代謝が改善されていきます。
■ トレーニング直後はMCT1が減る?
実は、高強度トレーニング直後には一時的にMCT1の量が減少することもあります。
これは一時的な現象であり、回復期に適切な刺激を繰り返すことでMCT1は増えていきます。
■ まとめ:MCT1は“乳酸再利用システム”のカギ
・MCT1は乳酸やピルビン酸を輸送するたんぱく質
・ATPを使わず濃度勾配で輸送される
・心筋や遅筋に多く存在
・持久力トレーニングで増加
・筋肥大や糖代謝とも関係
・糖尿病の改善にも関与する重要な要素
乳酸は“捨てるもの”ではなく、“使えるもの”。
そしてその再利用にMCT1が深く関わっていることを、ぜひ覚えておいてください。
※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。
症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。



コメント