こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
糖質=太る、というイメージを持っていませんか?
実際、糖質を摂りすぎると脂肪として蓄積されることもありますが、
その前段階で体内には“グリコーゲン”として蓄える仕組みが存在します。
特に重要なのが、「肝臓」に蓄えられるグリコーゲン。
この肝グリコーゲンは、ただの予備エネルギーではありません。
私たちの生命活動に不可欠な「血糖値の安定」や「脳のエネルギー供給」に深く関わっています。
では、筋肉に貯蔵される「筋グリコーゲン」とは何が違うのでしょうか?
運動後の糖質補給は、肝臓と筋肉、どちらのグリコーゲンに優先的に使われるのでしょうか?
今回は、ダイエットやトレーニングの成果を高めたい方にも役立つ
肝グリコーゲンの働きと糖質代謝の仕組みを、わかりやすく解説していきます。
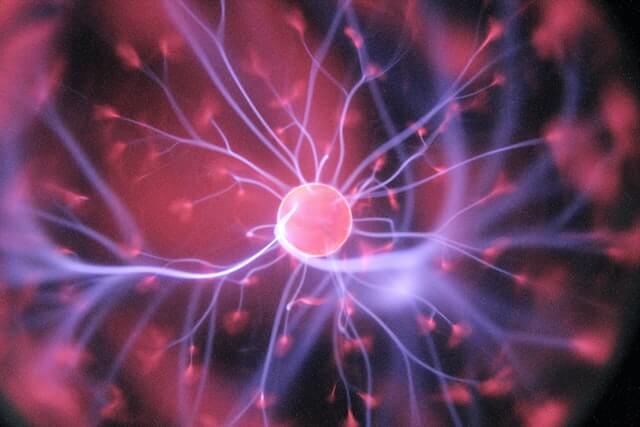
肝グリコーゲンとは?
糖質を摂りすぎると、体は余った分をそのままでは貯蔵できません。そこで、余分な糖質はグリコーゲンに変換され、肝臓や筋肉に蓄えられる仕組みがあります。
中でも、肝臓のグリコーゲンの主な役割は「血糖値の維持」です。
血糖値の安定に重要な働き
血糖値とは、血液中のグルコース(糖)の濃度のこと。通常、体はこの血糖値を一定に保つよう調整しています。
糖質を摂ると血糖値が上昇し、インスリンによって下がります。
糖質が入ってこないと、血糖値は自然と低下します。
ここで働くのが、肝臓に貯蔵されたグリコーゲンです。血糖値が下がってくると、肝臓内のグリコーゲンが分解されてグルコースとなり、血中に放出され、血糖値を維持します。
糖の流れ:食事から肝臓へ
たとえば「でんぷん(お米など)」を摂取した場合、以下のような流れになります:
- でんぷん(多糖類)は消化酵素で分解されて、単糖であるグルコースに。
- グルコースは小腸から吸収され、門脈を通って肝臓へ。
- 肝臓で一部が血液に送られ、一部がグリコーゲンとして蓄えられます。
肝臓と筋肉のグリコーゲンの違い
・肝臓:約500kcal分のグリコーゲンを貯蔵
・筋肉:約1500kcal分を貯蔵(個人差あり)
肝臓には「グルコース-6-ホスファターゼ」という酵素があり、グリコーゲンをグルコースに変換し血液へ放出できます。
一方、筋肉にはこの酵素がないため、血中へグルコースを出すことはできません。
筋グリコーゲンの役割と優先順位
筋グリコーゲンは、主に運動時のエネルギー源として使われるため、運動後には筋肉のグリコーゲンの補充が優先されます。
これは、「力を発揮する」という生存本能が背景にあると考えられます。
筋グリコーゲンが枯渇すると、カルシウムイオンの調節も乱れ、筋収縮に支障が出ます。
生きるためには“動ける体”が最優先。だからこそ、脳へのエネルギー供給よりも筋の回復が優先されるのかもしれません。
糖新生とは?
糖質が長時間体内に入ってこなかった場合、肝臓は「糖新生」により他の物質から糖を作るという策を取ります。
糖新生のポイント:
他の物質(乳酸・アミノ酸・グリセロールなど)→ピルビン酸 → オキサロ酢酸 → ホスホエノールピルビン酸
その後、一部は解糖系を逆向きに進んでグルコースが生成されます
コーリ回路と乳酸の再利用
運動時にできた乳酸は筋肉から肝臓に送られ、グルコースに再合成されることがあります。これを「コーリ回路」と呼びます。
ただし、乳酸を糖に戻すには多くのエネルギーが必要です。
そのため、運動中や直後はエネルギーの効率を優先し、乳酸はそのまま酸化されて再利用されるケースが大多数です。
・安静時や低強度運動時:肝臓で糖新生されやすい
・高強度運動時:肝臓の血流が減るため、糖新生が難しくなる
また、筋肉でもある程度は乳酸から糖を再合成する働きが見られます。
まとめ:肝グリコーゲンは血糖の守り役
肝グリコーゲンは、血糖値の安定と脳のエネルギー供給という大事な役割を担っています。
しかし、運動直後など生存に直結する「筋肉の力の回復」が求められるときは、筋グリコーゲンの回復が最優先されるというのが体の仕組み。
体は本当にうまくできています。
※本記事は、新R25に掲載された実績を持ち、トレーナー養成スクールの講師としても活動する井上裕司が監修しています。
健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断や治療を目的としたものではありません。
体調や症状に不安がある方は、必ず医師や専門の医療機関にご相談ください。
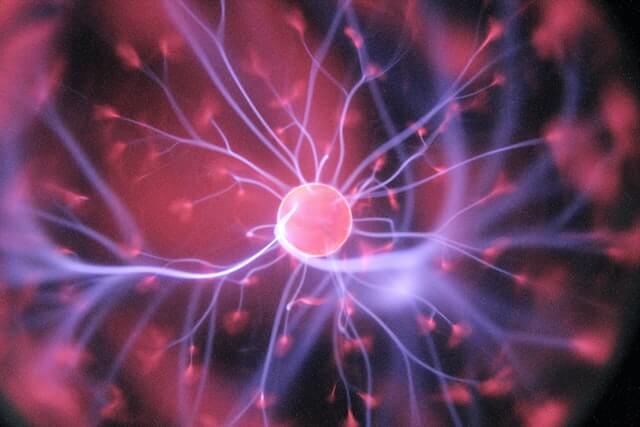


コメント