こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
「乳酸=疲労物質」と思っている方は多いかもしれません。
しかし、実際には乳酸はエネルギー代謝の自然な産物であり、その量は筋肉に蓄えられた糖質=グリコーゲンの量と深く関係しています。
今回は、乳酸とグリコーゲンの関係についてわかりやすく解説していきます。

高強度運動で乳酸が増えるワケ
運動時に糖質(グルコース)の利用を増やすには、高強度のトレーニングが効果的です。
例:全力ダッシュ・重量挙げなど
こうした高強度運動では、筋肉内にADP(アデノシン二リン酸)と無機リン酸(Pi)が蓄積します。
この蓄積がスイッチとなって、糖質の分解(解糖系)を一気に活性化させます。
その結果、
👉 ピルビン酸が急速に作られる
👉 ミトコンドリアでの酸化が追いつかない
👉 乳酸が多く産生される
という流れになるのです。
グリコーゲンが多いほど、乳酸も増える
運動中に作られる乳酸の“材料”は、主に筋肉に蓄えられたグリコーゲンです。
そのため、筋グリコーゲンの量が多いほど、より多くの乳酸が産生されやすくなると言えます。
逆に、長時間の運動を続けると筋グリコーゲンは減っていきます。
すると、後半になるにつれて乳酸は作られにくくなるのです。
「疲労=乳酸がたまったから」ではなく、実際には
・筋グリコーゲンの枯渇
・ADPや無機リン酸の蓄積
などが主な原因と考えられます。
運動開始直後も乳酸は作られている
「最初の10秒くらいはクレアチンリン酸でATPをまかなう」
という説明を聞いたことがあるかもしれません。
これは間違いではありませんが、実際には運動開始直後から乳酸も産生されています。
たとえば、50m走のような数秒間の運動でも、
・解糖系による乳酸の産生
・ミトコンドリアによる酸化反応
は同時に始まっています。
糖質の分解と乳酸の行方
糖質(グリコーゲン)の分解が急激に進むのは、あくまで短時間です。
なぜなら、
・グリコーゲンの貯蔵量には限界がある
・急激な分解が長く続けば、すぐに枯渇してしまう
つまり、運動の最初のうちは乳酸が一気に増えるものの、その後は自然と収まっていきます。
では、余分にできた乳酸はどうなるのでしょうか?
乳酸は「再利用」される
急激に作られた乳酸は、そのまま捨てられるわけではありません。
・一部は血液を通じて他の筋肉や心臓、肝臓へ
・ピルビン酸に戻されて、ミトコンドリアで酸化される(再利用される)
つまり、乳酸は“エネルギーの中継物質”として再び活躍するのです。
もちろん、すべてが即座に再利用されるわけではないので、
乳酸濃度はしばらく高いままになることもあります。
まとめ
・高強度の運動では糖質の分解が進み、乳酸が増える
・筋グリコーゲンが多いと、より多くの乳酸ができる
・グリコーゲンが減ると、乳酸も作られにくくなる
・乳酸は酸素があっても作られ、再利用もされる
・乳酸=疲労物質ではなく、エネルギー代謝の一部
乳酸は、体が効率的にエネルギーをやりくりするための重要なパートナー。
「疲労物質」というレッテルを貼るには、ちょっともったいない存在かもしれませんね。
※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。
症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

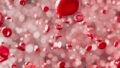
コメント