こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
「最近なんだか疲れやすい…」「立ちくらみが気になる」
そんな日常の体調の変化に気づいたとき、“貧血”という言葉が頭に浮かぶ方も多いかもしれません。
この記事では、貧血に関係すると言われている体内の仕組みや栄養素についての一般的な情報をわかりやすくまとめました。
普段の生活を振り返るきっかけや、食事のヒントとして参考にしてみてください。

そもそも「貧血」ってどういう状態?
日常会話でよく耳にする「貧血」という言葉。
これは、一般的に「体の中で酸素を運ぶ働きに関わる成分が少なくなっている状態」を指すことが多いようです。
体内の酸素運搬には、「ヘモグロビン」というたんぱく質が関与しているとされており、ヘモグロビンの材料には鉄が必要だとされています。
この鉄が不足すると、めまいや疲れ、集中力の低下などを感じるケースがあるといわれています。
よく話題になる「ヘモグロビン」と「フェリチン」
日常の健康チェックや検査で見かける数値の中に、「ヘモグロビン」や「フェリチン」があります。
- ヘモグロビン(Hb):体内で酸素を運搬するとされるたんぱく質
- フェリチン:体の中に蓄えられている鉄の貯蔵量を示すとされる指標
これらは、体調管理や栄養バランスの目安として注目されることがあります。
ただし、数値の判断や対処については、専門家による評価が必要です。
こんなとき、鉄に関心を持つ人が多いようです
鉄は私たちの体にとって欠かせないミネラルの一つとされており、性別や年齢、ライフスタイルによって必要量が変わることがあります。
たとえば以下のような場面で、鉄について意識する方が多いようです:
- 毎月のサイクルで体の変化を感じるとき
- 食生活が偏りがちだと感じるとき
- 運動量が多く、体の回復を意識したいとき
食事と栄養バランスの工夫でサポートできることも
日々の体づくりにおいては、「どんな栄養素をどのように取り入れるか」が重要なテーマの一つです。
鉄には、主に次の2つの種類があるとされています:
● ヘム鉄(動物性の食品に含まれる)
- 含まれる食品の例:赤身肉、魚(マグロ、カツオ)、レバーなど
- 一般的に吸収率が高いといわれています
● 非ヘム鉄(植物性食品に含まれる)
- 含まれる食品の例:ほうれん草、豆類、ひじき、小松菜など
- 吸収されにくい傾向がありますが、ビタミンCと一緒に摂るとサポートされるという情報もあります
その他、バランスを意識したい栄養素
| 栄養素 | 役割(一般的な働き) | 食材例 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 鉄の吸収サポート | ピーマン、柑橘類、ブロッコリーなど |
| ビタミンB6 | 健やかな血の材料作りに関与すると言われる | 鶏むね肉、バナナなど |
| ビタミンB12 | 赤血球の形成に関係するとされる | レバー、卵、魚介類など |
| 葉酸 | 細胞の働きに重要な栄養素として知られる | 緑黄色野菜、アボカドなど |
食生活での注意点(一般的な観点)
鉄を含む食品を意識して摂っていても、知らないうちに吸収を妨げてしまうケースもあるようです。
以下のような習慣については、あくまで一般的な観点から注意が必要とされることがあります:
- アルコールや冷たい飲み物のとりすぎ
- 加工食品の過剰摂取(リンの過剰摂取がミネラルの吸収に影響する場合も)
- 精製されていない穀物の大量摂取(フィチン酸がミネラルの吸収を阻害することがある)
サプリメントはどう考える?
最近では、鉄分を補えるサプリメントも数多く市販されています。
便利な反面、体質や摂取状況によっては過剰になる場合もあるため、使用する際は成分表示や容量をよく確認することが大切です。
健康に関わる製品を選ぶ際は、ご自身の体調や生活スタイルに合っているかをじっくり検討することが推奨されています。
自分の体調と向き合うきっかけとして
「朝起きるのがつらい」「気分が沈みがち」「疲れが抜けにくい」と感じたとき、
それが一時的なものなのか、生活リズムや栄養が関係しているのかを振り返ってみるのも一つの方法です。
日々の食事や習慣に少し意識を向けることで、より自分らしく過ごすためのヒントが得られるかもしれません。
まとめ:栄養バランスを意識した生活を無理なく続けよう
「貧血」という言葉に敏感になりすぎず、体調の変化に気づき、小さな見直しを重ねることが、自分のペースでできる健康づくりの一歩です。
- 食事は「バランス」を大切に
- 鉄だけでなく、複数の栄養素を意識
- 習慣を整えることが、心と体の安定にもつながる
気になる不調が続く場合は、医療機関に相談することも選択肢の一つです。
⚠️ ご注意:本記事は、一般的な生活習慣や栄養に関する情報の提供を目的としており、医療上の診断や治療、栄養指導を行うものではありません。体調や健康に関するご不安がある場合は、医師や専門家にご相談ください。

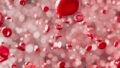

コメント