こんにちは!
トレーナー育成講師の井上裕司です。
「乳酸がたくさん出るのは、酸素が足りないから」
そう思っていませんか?
実は、乳酸が多く作られるかどうかは、酸素の有無よりも“糖質の分解量”がカギになります。
そして、糖質の分解には特定の酵素たちが深く関わっています。
今回は、糖代謝をコントロールする酵素「ホスホフルクトキナーゼ」や「グリコーゲンホスホリラーゼ」に注目して、
乳酸産生の仕組みをわかりやすく解説します。

◆ グリコーゲン分解の起点:グリコーゲンホスホリラーゼ
まず、筋肉に蓄えられたグリコーゲンを分解するためには、
✅ グリコーゲンホスホリラーゼ という酵素が必要です。
この酵素は、運動の強度に応じて
「不活性型」から
「活性型」に変化します。
特に、強度の高い運動では、
・ADP(アデノシン二リン酸)
・無機リン酸(Pi)
といった代謝物が多く産生され、それが引き金となって酵素が活性化します。
👉 運動強度↑ → ADP・Pi↑ → グリコーゲン分解↑ → 乳酸産生↑
このように、酸素が足りる・足りない以前に、「糖質がどれだけ分解されたか」が乳酸産生に直結しているのです。
◆ グルコース分解のカギ:ホスホフルクトキナーゼ(PFK)
次に登場するのが、グルコースの解糖系における律速酵素である
✅ ホスホフルクトキナーゼ(PFK)です。
このPFKも、ADPや無機リン酸によって活性化されやすいことがわかっています。
つまり、強度の高い運動でADPやPiが増えると、PFKの働きが強まり、糖質の分解がさらに進みます。
◆ 「pHが下がると酵素が働かない」は本当か?
ここでよくある誤解があります。
「乳酸がたまるとpHが下がり、ホスホフルクトキナーゼが働かなくなるのでは?」
実際、PFKはpHが7.0以下になると活性が低下するという性質があります。
このため、乳酸の蓄積によってpHが下がると、
「糖質が分解されづらくなるのでは?」と考えがちです。
◆ 実際は、ADPとPiの影響が大きい
確かに、pHの低下は酵素活性に影響しますが、
同時に運動中はADPと無機リン酸が大量に発生している状態です。
これらはホスホフルクトキナーゼの活性を強力に促進します。
したがって──
・pHが下がることで酵素活性が落ちる側面もある
・でも、ADPやPiの作用によってむしろ酵素が活性化されている
という相反する要素が同時に存在するのです。
そのため、「pHが下がる=酵素が働かなくなる」とは一概に言えません。
◆ まとめ
・乳酸の産生は酸素よりも「糖質の分解スピード」による
・グリコーゲンの分解は、ADP・Piの増加で活性化される
・ホスホフルクトキナーゼも同様に、ADP・Piによって活性化される
・pHが下がると酵素活性が落ちるが、それを上回る活性化作用が同時に働いている
・結果として、強度の高い運動では糖質が分解され乳酸が多く産生される
乳酸は「酸素不足だから出る」のではなく、
体がエネルギーを素早く生み出すために使った“証拠”でもあるのです。
筋トレや持久系の運動で「乳酸が出る=効いてる」という感覚は、
実はかなり正確な“生理学的サイン”だったりしますよ。
※本記事は、健康・栄養・トレーニングに関する一般的な情報提供を目的としており、医療上の診断・治療を目的としたものではありません。
症状や体調に不安がある場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。
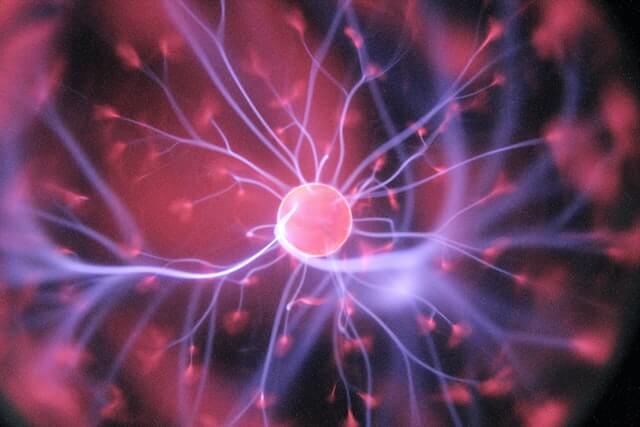

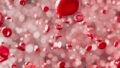
コメント